野球には戦術として意図的に打者を歩かせる場面があり、その方法の一つが「申告故意四球」です。
「申告故意四球」と「申告敬遠」は同じ意味を持ちますが、ふたつの表現方法はどのような使われ方の違いがあるのでしょうか。
そして、従来の故意四球との違いも理解することで、ルール改正の背景や試合戦略への影響がより明確になります。
特に高校野球やプロ野球では、導入時期や運用方法に差があり、選手や指導者の判断にも影響を与えてきました。
本記事では、申告故意四球の基本的な違いからスコア表記、高校野球とプロ野球の導入時期、さらには必要性やアナウンス方法まで解説します。
さらに、松井秀喜さんの5打席連続敬遠や、打者13人中11四死球、両軍合計41四死球といった高校野球の歴史的事例も取り上げ、ルールと記録の両面から申告故意四球を掘り下げます。
申告故意四球と申告敬遠の違いは?
申告故意四球と申告敬遠の違いは、名称の公式性と使われる場面にあります。
申告敬遠は日常的に使われている表現ですが、申告故意四球というのは聞きなれない人もいるでしょう。
どちらも投手が投球せずに審判へ意思を伝えることで四球を与える制度ですが、言葉の性質や記録上の扱いに違いがあります。
また、申告故意四球と従来の故意四球では投球の有無やリスク面にも差があります。
ここからは申告故意四球と申告敬遠について具体的に解説していきます。
申告故意四球と申告敬遠の違い
申告故意四球と申告敬遠の違いは、使われる場面によります。
結論から言うと、両者は同じ制度を指しますが、申告故意四球が公式な野球用語であり、申告敬遠は一般的な呼び方です。
敬遠の正式な表現が故意四球ということになります。
申告故意四球は、監督や捕手が審判に意思を伝えるだけで、投手が実際に4球を投げずに打者へ四球を与える制度です。
この制度について、報道やファンの会話で「申告敬遠」と表現され、使用されています。
制度そのものに違いはなく、違いがあるのは言葉の性質や使用場面です。
記録や公式発表では「申告故意四球」と記載されますが、ニュースや実況では「申告敬遠」と表現されることが多く、同じ行為でも呼び方が変わる点を理解しておくことが大切です。
申告故意四球と故意四球の違い
申告故意四球と故意四球の違いは、投球の有無とプレーの進行方法にあります。
結論として、申告故意四球は監督や捕手が審判へ意思を伝えるだけで四球が成立し、投手は1球も投げません。一方、故意四球は実際に4球のボールを投げて打者を歩かせる方法です。
申告故意四球はボールデッドの状態で進塁が確定するため、暴投や打者が敬遠球を打つといったリスクがなく、試合時間の短縮や投手の負担軽減に直結します。
故意四球はプレーが続行中に行われるため、球数が加算され、思わぬプレーが発生する可能性があります。
申告故意四球の導入によって選択肢は広がりましたが、状況によっては従来型の故意四球が選ばれる場合もあり、使い分けが戦術面で重要となります。
申告故意四球のスコア表記について
申告故意四球のスコア表記は、スコアブックに「DIB(Declared Intentional Base on Balls)」と記載されます。
DIBを詳しく和訳すると
- Declared:申告された(公式に宣言された)
- Intentional:意図的な、故意の
- Base on Balls:四球(フォアボール)
となります。
通常の四球や従来の故意四球と明確に区別されます。
通常の四球は「B」、従来の故意四球は「IB」と表記されるため、DIBという記号によって一目で違いが分かります。
申告故意四球は監督や捕手が審判に意思を伝えるだけで成立し、投球数に加算されず、暴投や打者のスイングといったリスクもありません。
日本プロ野球、高校野球と順次導入され、スコアの記録方法も統一されました。
記録者はこの表記を正確に使い分けることで、試合経過や戦術の意図を後から見ても明確に把握できるようになります。
申告故意四球の高校野球導入時期について
野球で申告故意四球が導入されたのはMLBがはじまりです。
高校野球が申告故意四球を採用した背景には、投球数削減による投手の故障防止や試合時間短縮の必要性がありました。
プロ野球や大学野球より遅れての導入となりましたが、どのような理由があったのでしょうか。
ここでは、高校野球とプロ野球それぞれの申告故意四球の導入時期と、導入理由や経緯について詳しく解説していきます。
高校野球の導入時期について
高校野球に申告故意四球が導入されたのは2020年です。
申告故意四球が導入された理由は、選手の健康管理と投球数削減を優先したためです。
申告故意四球は投球を省略できるため、無駄な球数を減らし、投手の故障防止につながります。
このときプロ野球や大学野球ではすでに導入されていましたが、高校野球は教育的配慮や運営面での混乱防止を考慮し、投球数制限の導入と同じ2020年に合わせて実施されました。
投球数制限とは、1人の投手が1週間に投げられる球数は500球以内というルールです。
ベンチワーク(ベンチ内の選手・スタッフがチームを円滑に動かすための支援や采配のこと)やアマチュア規則に沿った手順調整も必要だったため、慎重な準備期間が設けられたのです。
プロ野球の導入時期について
プロ野球に申告故意四球が導入されたのは2018年です。
結論として、この制度は試合時間の短縮と投手の負担軽減を目的に採用されました。
申告故意四球は監督や捕手が審判に意思を伝えるだけで四球が成立し、投手は1球も投げません。
従来の敬遠では4球を投げる必要があり、その間に試合進行が遅れたり、暴投や捕逸といったリスクが伴いました。
申告故意四球の導入により、こうした時間的・安全面の課題が解消され、戦術上も有利な状況を素早く作りやすくなりました。
MLBが2017年に導入した翌年、日本のプロ野球も同じ理由で制度化し、データ重視の現代野球にも適したルールとなりました。
ちなみに社会人野球、大学野球でも2018年に申告故意四球が導入されています。
申告故意四球はなぜ必要なのか
申告故意四球は、試合時間の短縮と選手の負担軽減のため必要とされ、導入されています。
従来のように4球を実際に投げる必要がなくなるため、無駄な投球を省き、試合運営をスムーズにします。
投球数が減ることで、投手の肩や肘への負担が軽減され、高校野球のようにひとりの投手が膨大な投球数になる大会では故障予防にも有効です。
また、投球時に起こり得る暴投や捕逸といった予期せぬ失点リスクも避けられ、安全性向上にもつながります。
効率性と安全性の両面で現代野球に適した制度といえます。
一方、なぜ申告故意四球を導入しなければならないのかという反対意見もあります。
あきらかな故意四球であっても、それを打とうとする打者がいたり、暴投や捕逸が生じることもひとつの観戦の楽しみであり、醍醐味でもあるからです。
なぜ省かれる時間は大した短縮にならないのに導入するのかという声もあるようです。
申告故意四球のアナウンスについて
申告故意四球は、甲子園球場のように場内アナウンスがある場合は「○番○○選手は申告故意四球により一塁へ進みます」と放送されます。
電光掲示板にも「申告故意四球」と表示されます。
手順としては、まず守備側の監督やコーチが球審に申告故意四球を申し出ます。
球審は受理後、大きなジェスチャーと明確な発声で一塁進塁を指示し、場内アナウンスがある場合は「○番○○選手は申告故意四球により一塁へ進みます」と放送されます。
打者は一度バッターボックスに入り、その後一塁へ進みます。
高校野球における正式な手順に基づき全員に分かる形で行われます。
放送設備がない球場では審判の動作と肉声で伝達されます。
こうして、申告故意四球は試合に関わる者と観戦する人に明確なアナウンスにより示された上で、投球を伴わず、ボールデッド状態で記録されるのです。
高校野球歴代の四死球について
高校野球では、申告故意四球や通常の四死球が戦況に大きな影響を与えた試合が数多く存在します。
歴史的には、松井秀喜さんが5打席連続で申告故意四球を含む敬遠を受けた試合や、打者13人に対して11個の四死球を記録した異例の展開、さらには両軍合計41個の四死球という前代未聞の記録もあります。
いずれも申告故意四球の戦術的側面や四死球の影響力を示す事例です。
ここでは歴史的記録のこれらの試合の詳細を試合経過等とともに解説します。
松井秀喜5打席連続敬遠
松井秀喜さんの5打席連続敬遠は、高校野球史上もっとも有名な四死球戦略の一つとして今も語り継がれています。
1992年夏の甲子園2回戦、星稜高校の4番打者だった松井秀喜さんは、明徳義塾高校から全打席で四死球を与えられ、一度も勝負してもらえませんでした。
厳密にいえば死球はなく、すべて四球のみのいわゆる故意四球でした。
特に7回表の走者なし場面での四死球は観客の強い反発を呼び、「正々堂々と勝負しろ」という声が飛び交いました。
この試合は申告故意四球がまだ存在しない時代で、全て投球による敬遠が行われましたが、その極端な作戦は勝利至上主義や高校野球の精神に関する全国的議論を巻き起こしました。
後年、この出来事は申告故意四球やスポーツマンシップの是非を考えるきっかけとなり、ルールや戦略面での重要な分岐点となりました。
打者13人に対し11四死球
1971年春の選抜高校野球2回戦の報徳学園高校(兵庫県)対東邦高校(愛知県)の試合で、報徳学園高校の金澤真哉さんが先発として投げた試合は、高校野球史に残る四死球の多さで知られています。
結果として打者13人に対し11四死球を与え、1回裏だけで11失点という異例の展開になりました。
試合序盤、先頭打者への死球から始まり、続く打者にも頭部死球、その後も連続四球で走者を溜め、無安打で大量失点を許しました。
頭部死球は日本プロ野球独自の「危険球退場ルール」にあてはまりますが、公認野球規則には一発退場は定められていませんので、投球は継続されました。
大乱調だった金澤さんは1回裏2アウトで交代となりましたが、その時点で打者は2周目の延べ13人11四死球となっていました。
当時は申告故意四球が存在せず、全ての四死球は制球難によるものでした。
この試合は精神的動揺が投手の投球を大きく崩す典型例として語り継がれ、同時に四死球の重さを改めて印象づける出来事となりました。
申告故意四球が導入された現代では、こうした極端な数字は滅多に見られません。
両軍合計41四死球
2017年の全国高校野球西東京大会5回戦で、日大鶴ケ丘高校と明治大学付属中野八王子高校が記録した両軍合計41四死球は、高校野球史でも極めて珍しい出来事です。
最終的に日大鶴ケ丘高校が19対15で逆転勝利しましたが、試合は4時間を超える長丁場となりました。
異常な四死球数の背景には、極端に狭いストライクゾーンと酷暑による体力消耗がありました。
この試合での四死球には申告故意四球はなく、全て実際の投球によるものでした。
結果的に、甲子園大会記録を大きく上回る数字が生まれ、プロ野球やメジャーリーグでも滅多に見られない事例として注目されました。
現在でも、申告故意四球の有無に関わらず、制球力と精神面の重要性を示す象徴的な試合とされています。
まとめ
申告故意四球は、試合時間短縮や投手の負担軽減、安全性向上といった目的を持つ重要な制度です。
申告敬遠との違いは名称の差であり、意味や手順は共通していますが、従来の故意四球との違いは投球を省略できる点にあります。
高校野球とプロ野球では導入時期が異なり、それぞれの競技環境やルール運用の背景も異なります。
また、スコア表記やアナウンス方法も規則に沿って統一されており、観客や関係者に誤解なく伝える工夫がされています。
松井秀喜さんの5打席連続敬遠や、打者13人中11四死球、両軍合計41四死球など、申告故意四球の是非や戦略性を考える上で示唆に富む事例も存在します。
これらの記録は、ルール改正の必要性や戦術選択の幅広さを示し、野球という競技の奥深さを物語っています。
申告故意四球は単なる省略ルールではなく、試合運営と戦術のバランスを取るための重要な仕組みと言えます。

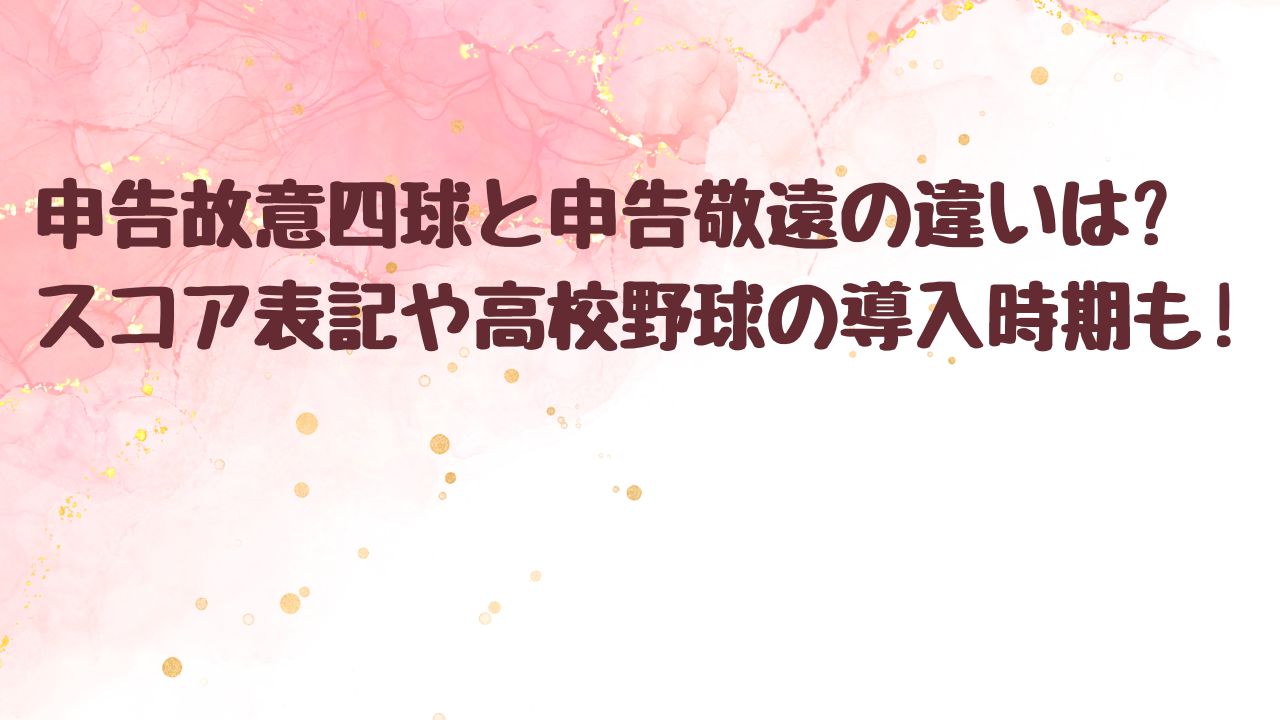
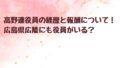
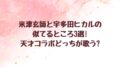
コメント